知的資産経営を学ぶ
知的資産経営の参考書籍
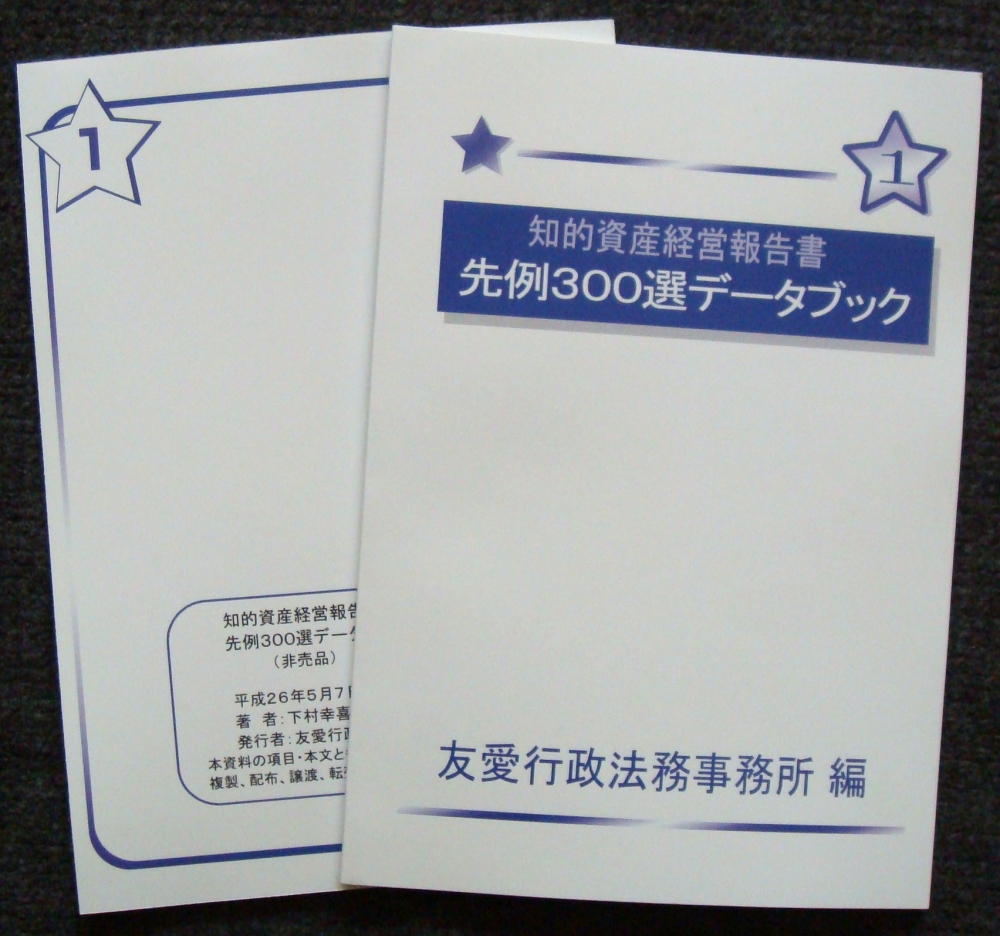
データブック作成のいきさつ
編者:下村幸喜
冷たい雨の日曜日、
暇をもてあまして、
知的資産経営報告書をいくつか読むことにした。
他の行政書士の先生方から、
あの会社のがいいとか、
あの事務所のは業界初だとか聞いていた
読み進めると案外おもしろい。
入手可能な知的資産経営報告書は約400
8ページのものもあれば、80ページのものもある。
平均すれば25ページくらいだろうか。
時間を忘れて読みふけると、
いつしか全部読んでいた。
そして手元には、それを簡潔にまとめた電子データが残った。
こんな風に行けば楽だったのに、
そうは行かない。
限られた時間の中で、どれを読めば参考になるのか、
例えば製造業と言っても、結局何の会社なのか
自分が小さな企業の報告書を作ろうとするのに
会社の歴史や規模が全然違うものはあまり参考にならない。まして各報告書のレイアウトや手法は分からない。
参考になる適当な資料はない。
読むための優先順位でもあれば良いがそれもない。
誰か作ってくれないかなぁ
手分けして作る協力者がいれば・・
だが打ち合わせ、評価基準の統一・・難しい。
ということで、結局、自分で全部読んで作ることにした。
報告書によって、自分が書いたメモもさまざまなので、
記載したメモの全部を冊子にすることは出来ない。
そこで、他の知的資産経営報告書を参考にしようとするとき、上に書いたような面倒を解消し、ムダな時間を省いて、自分が求めるものに短時間でたどり着ける。
そういう効果は期待できるものにした。
たぶん色々と役に立ちます!
知的資産経営報告書と支援者
知的資産経営報告書のデータブックを作ろうとして、
入手可能な知的資産経営報告書を片っ端から読む。
専門家の先生方の名もその報告書の作成支援者として記載されている。
問題意識を持って読んでいると、
なんだか、他の人の答案用紙をのぞき見ているような気になる。
もちろん、やましい事をしているわけではない。
そもそもこの資料は他人に読ませるために作成・公開されている。
それでも覗き見の感覚が生ずる原因は、
それを評価しようとしているからかもしれない。
これは先生が生徒の解答に○付けするのとは違い、
自分自身あるいはこれから知的資産経営報告書を作る人のために
参考にする優先順位の目安を付けるものだから、
報告書の出来、不出来をジャッジするものでも、
そこに記載された会社や経営者に優劣をつけようとするものでも、
支援者の能力を判断しようとしたものでも無い。
作成の際には、期間や目的、経営者や会社の都合により、
支援者自身が思っているようなものが出来ないまま
完成・公開せざるを得なかったものもあるのだろう。
同じ支援者でも、作成内容が大きく違う場合がある。
また同じ会社の報告書を同じ支援者が、
複数年にわたり作成協力したものでは、
前回は「○○の部分を工夫すべきだ」とこちらで評価したものが、
次回分では、その部分が改善され、
より分かりやすくなっているケースが多く、
作成支援者と認識が一致し、うれしく感じる。
こうしたことを感じながら読んでいると、
企業支援のため、報告書作成をどのように進めていくのかを考える材料が増えて行く。
------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------
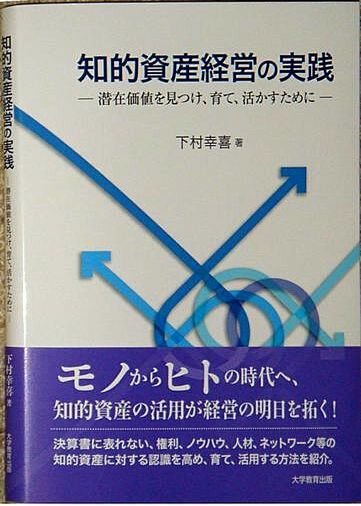
『知的資本経営の実践』
~潜在価値を見つけ、育て、活かすために~
著者:下村幸喜著
平成26年2月20日発売
価格:1800円+税
■インターネットでの購入サイト
「丸善Webサービス」
「セブンイレブン」など

------------------------------------------------------------------------------------------

「知的資産経営支援の強化書」
